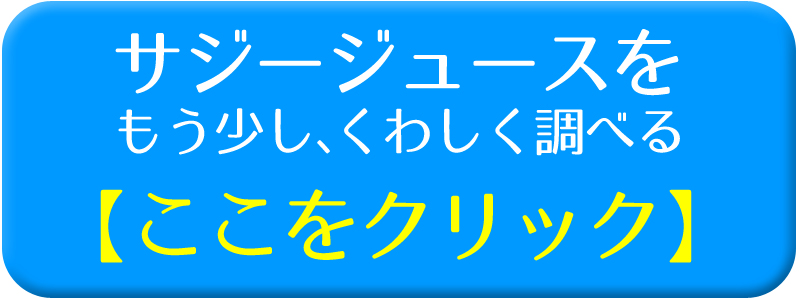おしっこのチクチクスッキリと解消するためには、4つのルールを覚えておこう
おしっこのチクチクはバイキンが膀胱の中で炎症する病気。でも、おしっこのチクチクになる人とならない人がいるんです。その差はおしっこのチクチクスッキリ解消する4つのルールを知ってるか知らないか。その4つのルールが簡単に守れるアイテムを紹介します。もうチクチクズーンにサヨウナラ!
バイキンや細菌は、実はどこにでもある。
空気中にも、下着にも、彼の手にもバイキンはあります。そして膀胱にはいってくることも、まあまああるのです。でも、全員がおしっこのチクチクになるわけではありません。
バイキンが入ってきても、炎症をおこす前にやっつける方法があります。

おしっこのチクチクスッキリと解消させる4つのルールって??
おしっこのチクチクスッキリと解消ルール
その1:免疫力を上げよう
バイキンが身体に入ってきたら、まずどうするか?身体はバイキンから身を守ろうとします。その身体の防衛力が「免疫力」と呼ばれるものです。
免疫は免疫学っていう学問があるくらい難しいものなんですが、簡単にいうとを「バイキンを外に出そう」としたり「やっつけたり」する力のことです。
この力、多くの人が生まれながらに持ってるものなのですが、免疫力が下がるような生活態度や、食事を続けていると弱まってきます。では免疫を上げるにはどうしたらいいのでしょうか?
おしっこのチクチクスッキリと解消してくれる免疫細胞とよばれるたくさんの種類の細胞が、身体の中でがんばっています。が、体温が下がると活動できなくなります。免疫力を下げないためには、体温を下げない努力が必要です。そのためにはどうすれば?

おしっこのチクチクスッキリと解消ルール
その2:体温を上げよう
体温が下がると働けない免疫力。逆に、体温が上がればどんどん力強くなります。
体温を上げるために一番大切なことは食事です。食べ物には身体を暖めるものと、冷やすものがあります。
寒い地方でとれるもの、冬場が旬のものは身体を暖めてくれます。コーヒーやお茶は一瞬身体を暖めてくれますが、それは温度の問題。しょうがとハチミツを混ぜたものなんかは効果的ですね。
身体を暖めるものがわかりにくいときは「冬の鍋料理」を思い浮かべるといいかもしれません。
もちろん、身体が冷えないようにキチンとお風呂に入浴したり、身体を締め付けて血行が悪くなるようなピタピタの服やデニムもよくありません。おなかを出したり、素足にミニスカートというのもおすすめできません。

おしっこのチクチクスッキリと解消ルール
その3:キナ酸を摂ろう
おしっこのチクチクスッキリと解消するにはクランベリーがいいという話をきいたことがあるかたもいるでしょう。クランベリーという果物には「キナ酸」という栄養素が含まれています。
キナ酸は身体の中で「馬尿酸」というものに変わり、膀胱のなかに入ってきたバイキンをやっつけてくれます。

おしっこのチクチクスッキリと解消ルール
その4:おしっこを、ちゃんと出そう
膀胱に入ったバイキンは、ドンドン数を増やして行きます。免疫力が高ければ、増殖をとめることもできますが、そうでない場合時間がたてばたつほどおしっこのチクチクはひどくなります。おしっこをためているということは、バイキンを捨てずに持っておくことと同じです。水分補給をしっかりして、おしっこを出しましょう。
おしっこのチクチクになるとおしっこのとき痛いですよね。だから、なんとなく避けたいのもわかりますが、ドンドン出して、バイキンが増えるのを薄めましょう。

【おしっこのチクチクスッキリと解消4つのルールまとめ】
おしっこのチクチクにならないようにするためには
★キナ酸のたっぷり入った食品をとる
★身体を暖める成分たっぷりの食品をとる
★免疫力を高める栄養素がたっぷり入った食品をとる
そんなに都合のいい食品、あるのでしょうか?
実はこのおしっこのチクチクスッキリと解消4つのルールのためにあるような天然果汁があるのです。
それは寒い寒い内モンゴルに自生してるサジーという果物です。サジーのもつ特徴はおしっこのチクチクスッキリと解消4つのルールとピッタリです。
サジーには
・おしっこのチクチクをなおす免疫力を上げるビタミンがたっぷり入ってます
・暴虎炎を治す免疫力を上げる、寒い地方の食べ物です
・おしっこのチクチクを治すキナ酸が、有名なクランベリーの2.2倍も含まれています
4の「水分補給」はできませんが、なんとこのサジージュース、水やジュースで割ったりして飲むこともできるのです。
おしっこのチクチクスッキリと解消してくれるサジージュース
「フィネスの黄酸汁 豊潤サジー」がおすすめです。
↓↓↓